先日、永江一石さんの書かれた「ネットがおもしろくてナニが悪い」という本を読んだ事を書きましたが・・
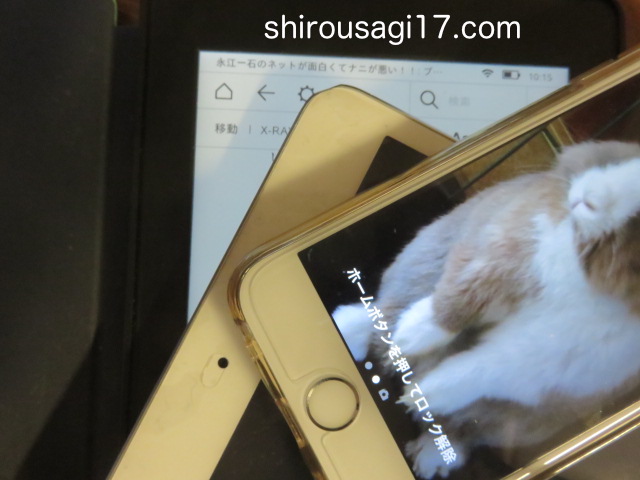
(この記事は書きたい、伝えたいと思ったことがうまく書けていないですね。修行します・・)
本当にこの本は面白くて、それから永江さんの書かれた他の本も読んでいます。
永江さんが他の本でもブログでも、警告しているのは情報弱者、情報リテラシーが低い人が多い事。
このことを読みながら思い出した、および考えた事を。

目をギラギラさせて 獲物がくるのを待つアメリカチョウゲンボウ。
その昔、私がドイツに来たばかりの頃(はや30年近く前)は、ドイツにはテレビ番組があまりありませんでした。
ARD、ZDF、それから地域の局の3つで、どれも国営でした。
放送時間は夕方から夜深夜にかかるまで。放送そのものはお昼頃から。しかも夕方までは前日の再放送などで、新しい番組はありませんでした。
テレビを持っていない家庭も結構多く、またインテリ、高学歴の親の家庭では「テレビを見るのはくだらない」といった風潮でした。
見るのは夜8時のARDのニュース、およびディスカッション番組、週末などに映画。(外国の映画の吹き替えは多かったですね)
日本から来たばかりの私にとってはこのテレビ放送が少ない、と言うのはとても不便でした。
と言うのは・・・
ちゃんとしたニュース番組があるとはいえ、それは夕方のみ。 日常生活に必要な情報ですら自ら積極的に仕入れないと入って来なかったのです。
例えば、ドイツにはサマータイムがありますが、いつからサマータイムが始まり、いつから終わるのか。町を歩いていても、誰も言うわけでもなく、ポスターがあるわけでもなく、テレビの放送は少ないし、映画などが放送されている時にテロップが流れるわけでもなかったのです。
ましてや、自分の興味あるもの、例えば、コンサート情報も、自ら専門誌を買って読む、とか、知っていそうな人に尋ねる。
ドイツにいても、ボ〜〜っとしていると何の情報も入って来ない、のです。
ここ最近20年くらいで、ドイツの様子がガラッとかわってしまいました。
テレビ放送も1日24時間。チャンネルの数も数えきれず、ラジオやテレビを見ていれば、まあ、ある程度の暮らしに必要な情報は入ってくるようになりました。
しかし、人それぞれ興味のある事が違うためもあるのか、日本だと「誰でも知っている」といった事、例えばオリンピックの開催日など、オリンピックに興味ない人はオリンピックに関する情報を仕入れようとしないので、知らない人は知らない、といった様子です。 (なので、日本ほど、こちらではオリンピック騒ぎはありません)
日本では、その昔は、ネットがない時代は、新聞、テレビ、それからラジオから情報を得ていたので 少なくともテレビから受け身であらゆる情報を得ることが出来た、と思います。
ところが、ネットの時代になって、テレビで受け取る情報のクオリティーが下がったのではないでしょうか?(実際に日本に住んでいないので、思い違いかもしれませんが。一時帰国の際にそう感じます)
また、新聞から情報を得ることが少なくなったことについては、上記の本の著者・永江一石さんが書かれています。(どこに書かれていたかちょっと思い出せないので、引用できず申し訳ありません。)
長い間、テレビなどの受け身で情報を得られる生活ができた日本。
ネットが主流になったと思われる今、自ら能動的に情報を探し、かつ、その情報が正しいか、自分で判断する力はとても必要だと感じます。



コメント