東西ドイツが統一されてからすでに30年以上が経過。
「え?ドイツって東西に分裂されていたの?」という方も少なくないのではないか?と思うこの頃です。
その東西分裂されたドイツの東側、東ドイツ(ドイツ民主主義共和国・略称DDR)は当時のソ連支配下にあり、学校で子どもたちが最初に習う外国語はロシア語、ドイツ語の中にもほとんど英語由来のものはありませんでした。
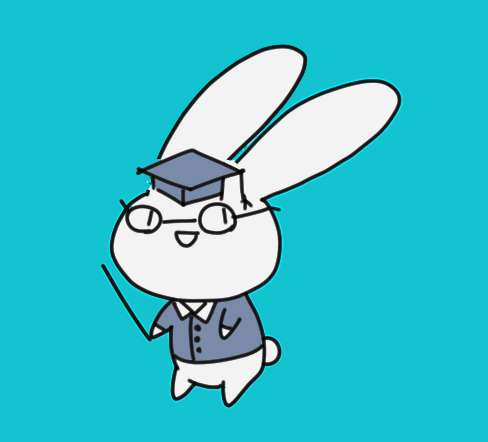
30年前は西ドイツでもそれほど英語は使われていなかったけれどね
そんな東ドイツで唯一と言っていいほど使われていた英単語が
Juice (der/das)
なのです。
Saftは果汁100%
Juiceは日本でもよく使われる単語ですよね。そうです、「ジュース」です。
ジュースに当たるドイツ語は
Saft(der Saft)です。
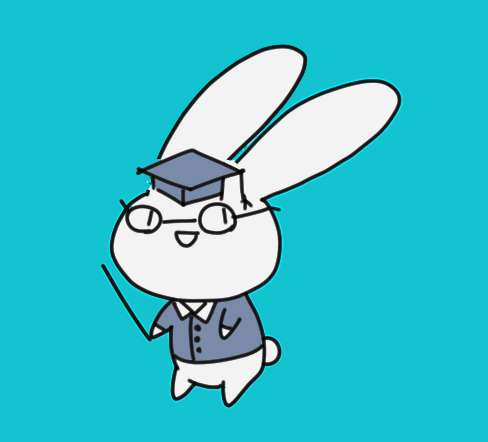
Saftの意味は果汁だけではなくて、
(動植物の組織内部に存在する液体、例えば)樹液
(野菜や果物などの)ジュース
という意味なので気をつけてくださいね!
そしてSaftといえば、果汁100%のジュース(厳密には100%にならないものもあるけれど)です。
オレンジが手に入らないから
Saftという単語は私がドイツに来てすぐによく耳にしていました。
食卓にはミネラルウォーター(炭酸水の場合がほとんどだった)、Saft(りんごやオレンジがメイン)が置かれていて、食事の際には「果汁100%は濃いすぎる!」と思えば、Saftを炭酸水で割って「Apfelschorle」(アップルジュース+炭酸水)や「Orangensaftschorle」(オレンジジュース+炭酸水)に。
ところが東独に行くと、Saftという単語をほとんど耳にしない。
レストランなどで飲み物を注文しているのを聞くと
「Juice」
と言っているではありませんか!
出てきたのはうっすらとオレンジ色をした飲み物。
「東ドイツと西ドイツのドイツ語が多少違うとは聞いていたけれど、ここ東ドイツではSaftって言わずにJuiceなのかな?」
くらいにしか疑問に思っていなかったのです。
が、今頃になって思うのは、
ドイツでは寒くてオレンジは育たない。
オレンジジュースを作るには南の国からオレンジを輸入しなくてはならない。けれど、当時東独には外貨がない。
外貨がないと外国から物を輸入することはできない。
オレンジを輸入することができなければ、当然、オレンジ果汁100%のSaftを作ることは出来ない。(作るととても高価)
そこでオレンジ果汁を薄めた飲み物を提供することにした。
果汁100%ではないから「Saft」とは名乗れない。
そこで、英語のJuiceという名前にして普及させた。
・・・というわけではなかろうか。
東独出身者に尋ねたら
「え?Juice?そんなものあったっけ?果汁入っていたのかなあ?」
すっかり忘れてしまったようです。
あの薄いオレンジ色の飲み物に果汁が1%でも入っていたのかどうかは私にはわかりません・・・
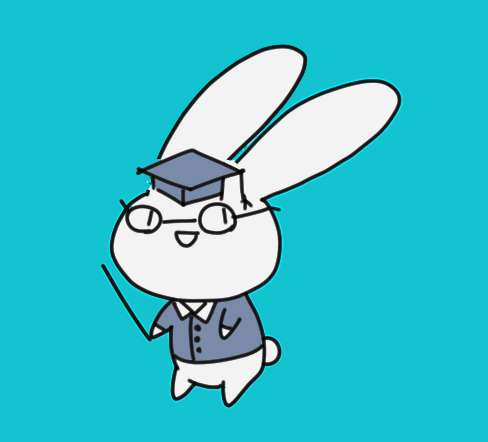
果汁を使った飲み物は果汁の含まれる割合によって
- Fruchtsaft
- Fruchtnektar
- Fruchtsaftgetränke
と言いますよ。
にほんブログ村



コメント